カーコンプレッサー製造現場で経験した苦い失敗と成功体験
幼少期より私は機械に触れることが多かった。農家だった実家はトラクターや稲刈り機、チェーンソー、草刈機などの農機器が沢山あり、壊れたら自分で修理をし、また使うの繰り返し。その影響もあり、工業高校へ進路を決めた。そこには沢山の工作機械があり、「ものづくり」の楽しさを肌で感じながら工業系の専門科目を学んだ。卒業後は、某自動車部品をつくる会社へ就職。カーコンプレッサー用部品の製造に改善班の一員として携わり、実に7年間勤めた。現在は物流クレーンをメンテナンスする仕事をしているが、最初の自動車部品製造会社での数々の体験が印象に残っており、今となっては多くのことを学ばせてもらったと感じる。
ちなみに、カーコンプレッサーとは名前の通り、自動車に載っているコンプレッサー(空気圧縮機)のことだ。コンプレッサーが生み出す圧縮空気のエネルギーを利用することで、空気の加熱あるいは冷却を行い、車の冷暖房(エアコン)機能を担う。実は日本で車にエアコンが標準装備されるようになったのは、1970年後半〜1980年代と歴史は浅い。しかし、今となっては必需品で、使ったことがない人はいないだろう。では、車内環境を快適に保つこのカーコンプレッサーのどの部品の製造に携わっていたのか説明していく。
私が配属された工場では、カーコンプレッサーのハウジングという部品を製造していた。ハウジングとは、コンプレッサーの外枠のアルミ素材で作られた筐体部品のことを指す。
工場は国内でも屈指の規模。24時間体制で稼働しており、1日に約1200台のハウジングを製造していた。もちろん製造量だけでなく、安定した品質を維持するため、様々な取り組みもされていた。
たとえばコンプレッサーのような機械は1/100ミリ、部位によっては1/1000ミリ単位の精度の加工が求められる。しかし、筐体はアルミ製のため、熱による膨張や凝縮の影響が大きく出てしまう。対策として、加工ズレが生じないように、機械とアルミの温度をこまめに管理した。
また、ハウジングの細部を形作る切削加工のあとは、アルミの粉(切粉)も残留する。そこで、刃物の回転速度や送り速度を計算し、切粉が除去されるように設定する。こういった創意工夫を重ねることで、ようやくハウジングという部品の品質は保たれるのだ。
ところで、一般的に工場と聞くと、上述したような制御を行えば、あとは大量の機械が自動で製品の加工を行なっていくように想像するだろう。もちろん、そういった側面もある。が、製品の仕様変更、工場設備の変更、機械の老朽化、そして変動する人員体制に対応しつつ、品質や製造を納期通りに保つことが、現場ではとにかく大変だった。
ちなみに私は工場全体の改善班の一員として携わっていたのだが、特に機械の老朽化への対応には気を引き締めていた。これはなぜか?簡単にいえば、工場設備は日に日に変化するのだ。例を挙げると、たとえば包丁を毎日使用すると、刃が摩耗し、切れ味が落ちる。このような現象は工場機械のあらゆるところで起きる。包丁が摩耗して、野菜や肉が切れなくなるように、工場の機械も老朽化に伴い加工精度が落ちていく。結果的に製品の不良につながる。
もちろん、過去の経験を頼りに、問題を早めに対処できるケースもあるが、全てではない。仕様変更に応じた状況の変化や、初めて壊れる箇所など、無数に問題はでてくる。それが大量の機器を運用し、複雑な製品を製造する上での難しいポイントだ。
機械の老朽化には最善の注意が必要なことは、わたしもこの身を持って経験した。入社して3数年目のころ、新しいコンプレッサー製品の品質検査の担当に就いた。そんなある日、後工程で組み付け不可というクレームが起きた。理由は筐体に致命的なキズが入っていたためで、私が見落としてしまったのた。キズの原因は、検査する前段階の加工の際、製品が置かれる基準台に老朽化による傾きが生じていたことだ。
幸い、車に取り付ける前で大惨事は防げた。が、クレームが出る前に製造された製品すべてを廃棄するとなると、損失は数百万円を軽く超えた。そのため、在庫品数千台を一つずつ確認することになった。
決して仕事の手を抜いていたわけではない。品質検査チェック項目を適宜見ながら行った。私の言い分として、その新しいコンプレッサー製品は今までとは異なった構造で、クレームの出た部位は既存の検査項目に入っていなかったのだ。つまり、今回の基準台の老朽化に伴う傾きの誤差は、これまで重視されない箇所だった。さらに、出たキズも目を凝らさないとわからない所で「正直こんなの分からないよ」と言いたい気持ちだった。
そうは思いつつも、工場長や各部署の上役が集まりだした。あれこれと発生状況の調査やなぜ見逃したのか事情聴取され、事態は大きくなった。「下手したら減給、あるいは解雇か」そんなこと思いながら血の気がひいていた。その後は、毎日のように工場長がラインに訪れては、「人的な問題はなかったのか」と張りつきながらの確認が行われた。さらに品質検査動作の確認や作業手順の間違いの有無など、1週間にわたり、各所で念入りな調査も入った。
不幸中の幸いか、今回は私の人的問題というよりは、品質検査チェックシステムに根本的な問題があったと判断された。さらにキズがついた製品に関しては、各部署の経験豊富な上役が連携をとり、「後工程の修正でなんとかなるのはないか?」と工夫をひねり出し、なんとか難を免れられた。
のちに思い返すと、品質検査の本質が理解できていなかったように思う。新しいコンプレッサー製品の製造となると、重視すべき箇所も変わりうる。当然、それを想定して検査チェック項目の追加を上司に提言しなければならなかった。さらに、そのチェック項目箇所の追加に応じて、これまで対応する必要がなかった老朽化に伴う機械の誤差を、他部署も含めて確認すべきだった。こういった日々の改善を重ねながらノウハウを蓄積することで、生産ラインは次の課題に対応するレベルへと成長していくのだろう。
そして何より、自分の意識にも問題があった。品質検査の担当は、品質を守る最後の砦であるが、どこか品質に関して、「問題なんて出ないだろう」と、疎かに考えていた自分がいたことに気づいた。だからチェック項目のみの確認という、受動的な仕事しかできていなかったのだろう。表現は難しいが、「問題は必ず起きる。それを探し出す。」という攻めの心理こそ、検査では重要に感じた。
思い返すと、このあたりから「ここの老朽化は今でこそ重要ではないが、もしココの誤差が拡大したら、話は変わるのではないか?」といった、観察力や疑問を重ねる探求心も湧いてきたと記憶している。
そしてこういった悔しい経験を経て、1年後にようやく工場に貢献できるようになる。それが「着座異常」の改善に取り組んだときの話だ。
まず「着座異常」を説明する。製品は加工される際、マシニングの基準座といわれる台座の上に置かれる。その後、製品が動かないよう、台座に油圧で押し付けられるのだが、工程途中で生じた切粉が台座と製品の間に挟み込んでしまうケース(これが「着座異常」)がある。この切粉が挟まってしまうと、製品は歪んだ状態で置かれることになり、加工にズレが生じるのだ。
切粉の大きさは数ミリ程度だが、製品を管理している公差は1/100ミリ単位。つまり、たった数ミリでも製品に大きな影響を与える。「着座異常」の対応はラインオペレーターが行い、多い時には1時間に何十回と起きる。対処時間は10秒くらいで長くはないが、この対応をするたびに生産台数が落ちてしまう。クリティカルでないものの、そのときは頻度が増えており、ラインを悩ますなかなか厄介な問題になっていた。
そこで私が取り組んでみた。他部署に相談してアイディアを出し合いながら、協力して改善に務めた。切粉の排除のための切削油の吐出口角度の調整や、刃物の回転数の増減など対策を練っては、実行の繰り返し。しかし、何をしてもなかなか効果が出ない。何なら完全に負のサイクルに入っていた。
そんなある日、「着座異常」の原因となっている切粉の種類を特定するため、切粉採取を行っていた。が、その工程では出るはずの無い切粉の種類が混ざっていることに気づく。その後、切粉の形状から工程を割り出してみた。すると、一つ前の工程にある洗濯機と呼ばれる切粉を除去するための設備(エアーの出るノズルを回転させ、切粉を吹き飛ばす)が動いていないことが判明した。原因は、ノズルの目詰まりと回転させるベアリングの経年劣化。この設備は目につかない位置にあり、それまで故障もなかったことから、これまで見落とされていたのだろう。修理後は、見事に「着座異常」が減った。加えて、月一回の設備点検項目にも追加することで、社内全体で意識を共有することができ、生産ラインの成長に僅かながら貢献できた。
この改善の試みは自らリーダーシップをとってできた、当時としては貴重な成功体験。切粉を採取していた際、観察や疑問を重ねられたことが解決の糸口になったように思う。以前の失敗経験を活かしきれた瞬間だ。さらにラインの問題は当工程だけが原因という固定観念を払拭でき、前後の工程にも意識を向けられるようになった。工場ラインで向き合うための、自分なりのロジックが出来上がった経験でもある。
現在は物流クレーンのメンテナンスをしているが、前職での苦い経験や成功体験が活きていると感じる。物流とは社会を支える大事な業種であり、もしクレーンが故障すると日用品や食べ物が私たちの手元に届かず、日々の生活に影響を与えてしまう。私は、前職の失敗を活かし常に疑いを持ってクレーンを点検、問題箇所を見つけ「ここの部品は大丈夫であろう」などの安易な考えを持たないようにし、チェック項目に入っていない箇所の点検、五感を常に使い問題箇所の早期発見を心がけている。この意識改革は、前職で経験した失敗したからこそ学ぶことができ、私にとって一生の宝物だ。
会社では、さまざまな専門用語が飛び交い、設備によって都度専門知識を学ぶ必要がある。が、改善や修理できた時の達成感もひとしおだ。なにより、少しずつ増えていく経験や知識が私にとって大きなモチベーションになっている。
苦労することや嫌なこと、失敗もある。が、経験は宝であり、諦めず取り組むことが最も重要に感じる今日この頃だ。
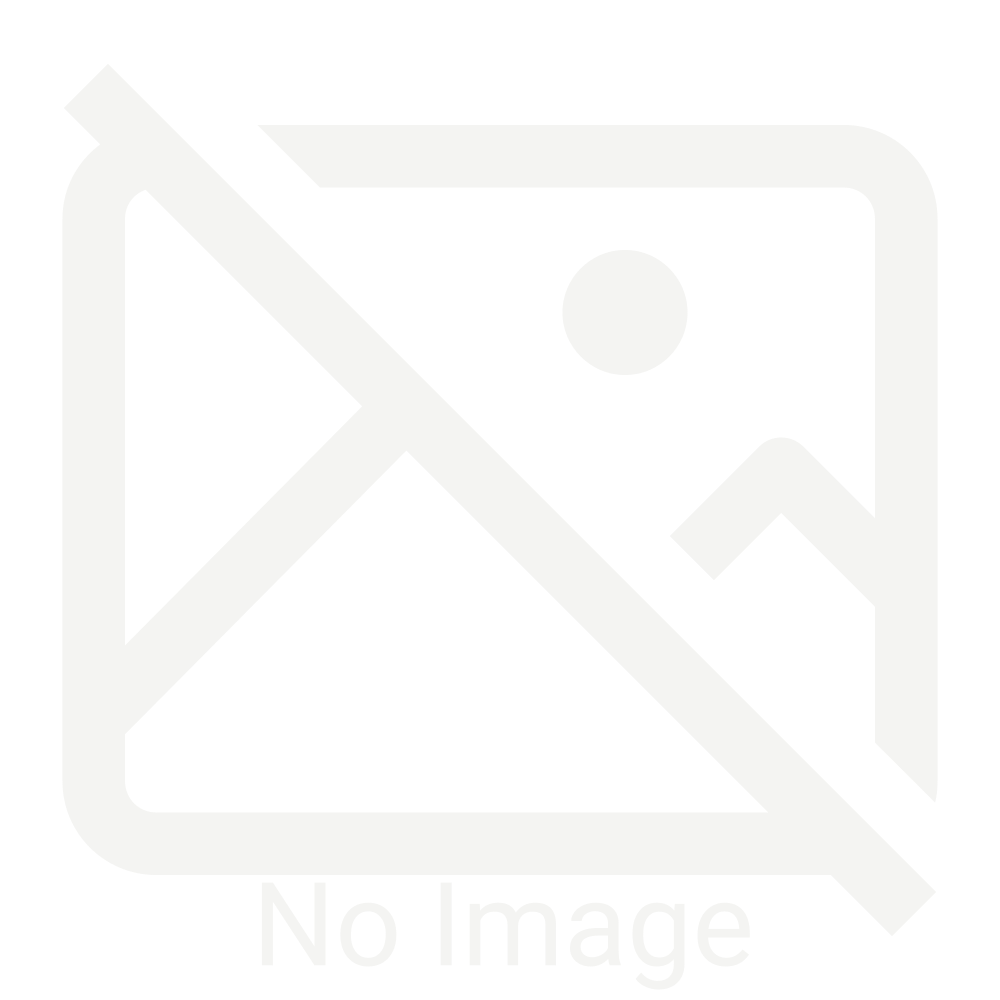
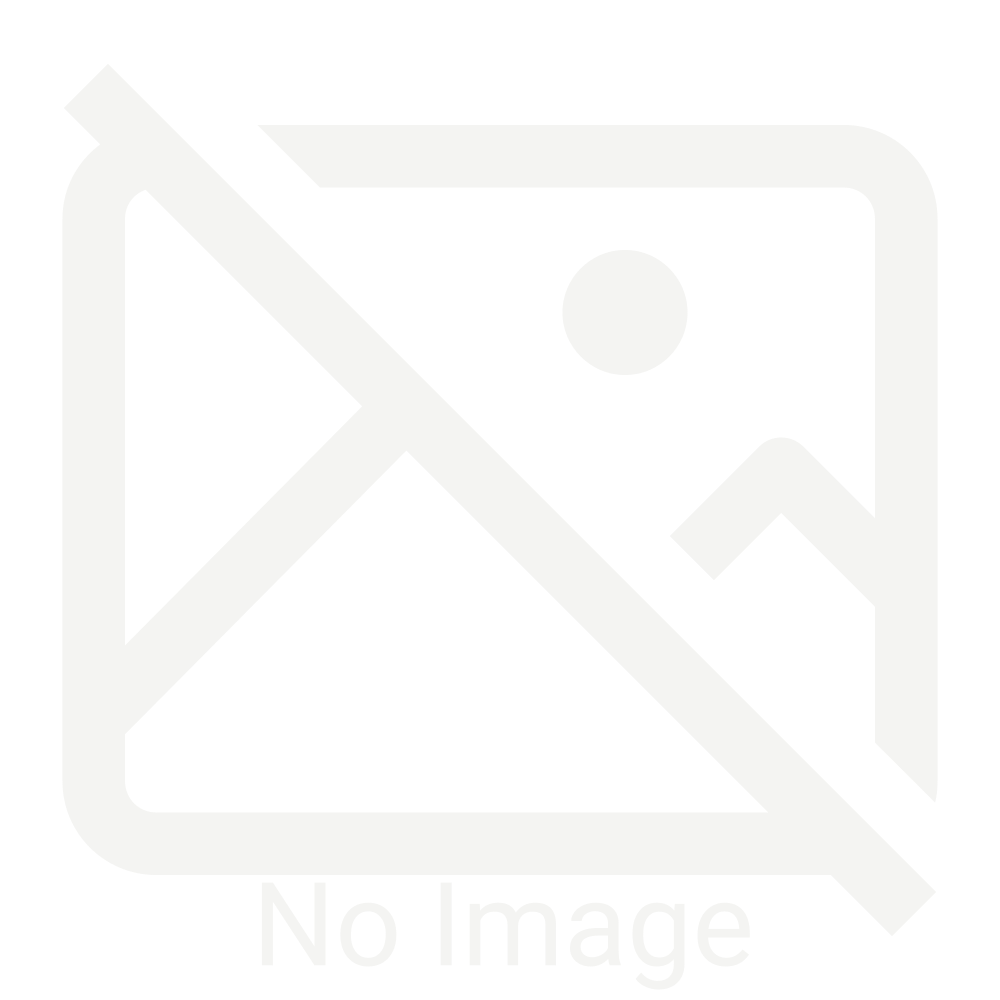
筆者紹介
私の性格は、明るく活発的です。
チャレンジしてみたいと思うことがあれば、
まずはやってみる事を意識しています。
なぜなら、人生は限られているので20年後、50年後に「あの時…挑戦すればよかった…」
と後悔したくないので、まずは迷う前に行動するようにしています。
また、「後悔したくない」というところでは、人との繋がりも同様です。
仕事やプライベートで会った人は、積極的に声をかけてコミュニケーションをとり、一期一会を大切にしています。
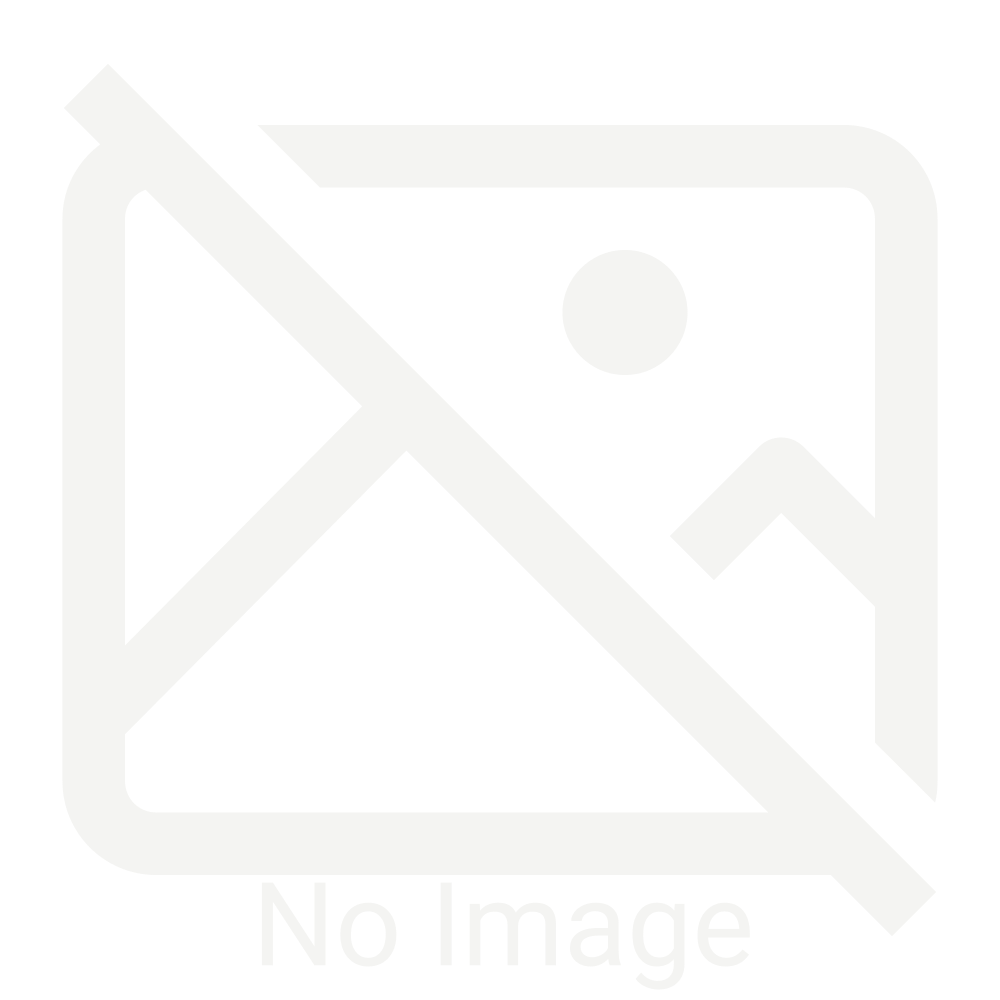
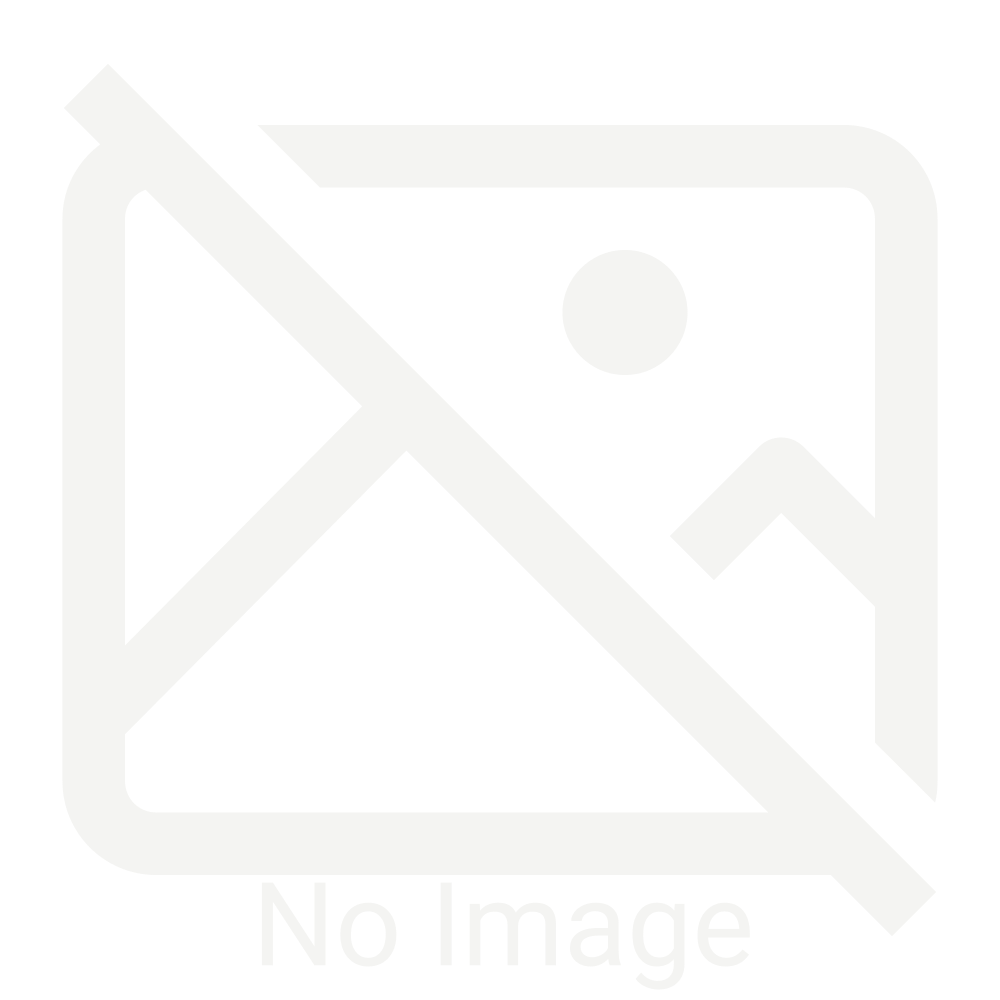
カーコンプレッサー製造現場で経験した苦い失敗と成功体験
ちなみに、カーコンプレッサーとは名前の通り、自動車に載っているコンプレッサー(空気圧縮機)のことだ。コンプレッサーが生み出す圧縮空気のエネルギーを利用することで、空気の加熱あるいは冷却を行い、車の冷暖房(エアコン)機能を担う。実は日本で車にエアコンが標準装備されるようになったのは、1970年後半〜1980年代と歴史は浅い。しかし、今となっては必需品で、使ったことがない人はいないだろう。では、車内環境を快適に保つこのカーコンプレッサーのどの部品の製造に携わっていたのか説明していく。
私が配属された工場では、カーコンプレッサーのハウジングという部品を製造していた。ハウジングとは、コンプレッサーの外枠のアルミ素材で作られた筐体部品のことを指す。
工場は国内でも屈指の規模。24時間体制で稼働しており、1日に約1200台のハウジングを製造していた。もちろん製造量だけでなく、安定した品質を維持するため、様々な取り組みもされていた。
たとえばコンプレッサーのような機械は1/100ミリ、部位によっては1/1000ミリ単位の精度の加工が求められる。しかし、筐体はアルミ製のため、熱による膨張や凝縮の影響が大きく出てしまう。対策として、加工ズレが生じないように、機械とアルミの温度をこまめに管理した。
また、ハウジングの細部を形作る切削加工のあとは、アルミの粉(切粉)も残留する。そこで、刃物の回転速度や送り速度を計算し、切粉が除去されるように設定する。こういった創意工夫を重ねることで、ようやくハウジングという部品の品質は保たれるのだ。
ところで、一般的に工場と聞くと、上述したような制御を行えば、あとは大量の機械が自動で製品の加工を行なっていくように想像するだろう。もちろん、そういった側面もある。が、製品の仕様変更、工場設備の変更、機械の老朽化、そして変動する人員体制に対応しつつ、品質や製造を納期通りに保つことが、現場ではとにかく大変だった。
ちなみに私は工場全体の改善班の一員として携わっていたのだが、特に機械の老朽化への対応には気を引き締めていた。これはなぜか?簡単にいえば、工場設備は日に日に変化するのだ。例を挙げると、たとえば包丁を毎日使用すると、刃が摩耗し、切れ味が落ちる。このような現象は工場機械のあらゆるところで起きる。包丁が摩耗して、野菜や肉が切れなくなるように、工場の機械も老朽化に伴い加工精度が落ちていく。結果的に製品の不良につながる。
もちろん、過去の経験を頼りに、問題を早めに対処できるケースもあるが、全てではない。仕様変更に応じた状況の変化や、初めて壊れる箇所など、無数に問題はでてくる。それが大量の機器を運用し、複雑な製品を製造する上での難しいポイントだ。
機械の老朽化には最善の注意が必要なことは、わたしもこの身を持って経験した。入社して3数年目のころ、新しいコンプレッサー製品の品質検査の担当に就いた。そんなある日、後工程で組み付け不可というクレームが起きた。理由は筐体に致命的なキズが入っていたためで、私が見落としてしまったのた。キズの原因は、検査する前段階の加工の際、製品が置かれる基準台に老朽化による傾きが生じていたことだ。
幸い、車に取り付ける前で大惨事は防げた。が、クレームが出る前に製造された製品すべてを廃棄するとなると、損失は数百万円を軽く超えた。そのため、在庫品数千台を一つずつ確認することになった。
決して仕事の手を抜いていたわけではない。品質検査チェック項目を適宜見ながら行った。私の言い分として、その新しいコンプレッサー製品は今までとは異なった構造で、クレームの出た部位は既存の検査項目に入っていなかったのだ。つまり、今回の基準台の老朽化に伴う傾きの誤差は、これまで重視されない箇所だった。さらに、出たキズも目を凝らさないとわからない所で「正直こんなの分からないよ」と言いたい気持ちだった。
そうは思いつつも、工場長や各部署の上役が集まりだした。あれこれと発生状況の調査やなぜ見逃したのか事情聴取され、事態は大きくなった。「下手したら減給、あるいは解雇か」そんなこと思いながら血の気がひいていた。その後は、毎日のように工場長がラインに訪れては、「人的な問題はなかったのか」と張りつきながらの確認が行われた。さらに品質検査動作の確認や作業手順の間違いの有無など、1週間にわたり、各所で念入りな調査も入った。
不幸中の幸いか、今回は私の人的問題というよりは、品質検査チェックシステムに根本的な問題があったと判断された。さらにキズがついた製品に関しては、各部署の経験豊富な上役が連携をとり、「後工程の修正でなんとかなるのはないか?」と工夫をひねり出し、なんとか難を免れられた。
のちに思い返すと、品質検査の本質が理解できていなかったように思う。新しいコンプレッサー製品の製造となると、重視すべき箇所も変わりうる。当然、それを想定して検査チェック項目の追加を上司に提言しなければならなかった。さらに、そのチェック項目箇所の追加に応じて、これまで対応する必要がなかった老朽化に伴う機械の誤差を、他部署も含めて確認すべきだった。こういった日々の改善を重ねながらノウハウを蓄積することで、生産ラインは次の課題に対応するレベルへと成長していくのだろう。
そして何より、自分の意識にも問題があった。品質検査の担当は、品質を守る最後の砦であるが、どこか品質に関して、「問題なんて出ないだろう」と、疎かに考えていた自分がいたことに気づいた。だからチェック項目のみの確認という、受動的な仕事しかできていなかったのだろう。表現は難しいが、「問題は必ず起きる。それを探し出す。」という攻めの心理こそ、検査では重要に感じた。
思い返すと、このあたりから「ここの老朽化は今でこそ重要ではないが、もしココの誤差が拡大したら、話は変わるのではないか?」といった、観察力や疑問を重ねる探求心も湧いてきたと記憶している。
そしてこういった悔しい経験を経て、1年後にようやく工場に貢献できるようになる。それが「着座異常」の改善に取り組んだときの話だ。
まず「着座異常」を説明する。製品は加工される際、マシニングの基準座といわれる台座の上に置かれる。その後、製品が動かないよう、台座に油圧で押し付けられるのだが、工程途中で生じた切粉が台座と製品の間に挟み込んでしまうケース(これが「着座異常」)がある。この切粉が挟まってしまうと、製品は歪んだ状態で置かれることになり、加工にズレが生じるのだ。
切粉の大きさは数ミリ程度だが、製品を管理している公差は1/100ミリ単位。つまり、たった数ミリでも製品に大きな影響を与える。「着座異常」の対応はラインオペレーターが行い、多い時には1時間に何十回と起きる。対処時間は10秒くらいで長くはないが、この対応をするたびに生産台数が落ちてしまう。クリティカルでないものの、そのときは頻度が増えており、ラインを悩ますなかなか厄介な問題になっていた。
そこで私が取り組んでみた。他部署に相談してアイディアを出し合いながら、協力して改善に務めた。切粉の排除のための切削油の吐出口角度の調整や、刃物の回転数の増減など対策を練っては、実行の繰り返し。しかし、何をしてもなかなか効果が出ない。何なら完全に負のサイクルに入っていた。
そんなある日、「着座異常」の原因となっている切粉の種類を特定するため、切粉採取を行っていた。が、その工程では出るはずの無い切粉の種類が混ざっていることに気づく。その後、切粉の形状から工程を割り出してみた。すると、一つ前の工程にある洗濯機と呼ばれる切粉を除去するための設備(エアーの出るノズルを回転させ、切粉を吹き飛ばす)が動いていないことが判明した。原因は、ノズルの目詰まりと回転させるベアリングの経年劣化。この設備は目につかない位置にあり、それまで故障もなかったことから、これまで見落とされていたのだろう。修理後は、見事に「着座異常」が減った。加えて、月一回の設備点検項目にも追加することで、社内全体で意識を共有することができ、生産ラインの成長に僅かながら貢献できた。
この改善の試みは自らリーダーシップをとってできた、当時としては貴重な成功体験。切粉を採取していた際、観察や疑問を重ねられたことが解決の糸口になったように思う。以前の失敗経験を活かしきれた瞬間だ。さらにラインの問題は当工程だけが原因という固定観念を払拭でき、前後の工程にも意識を向けられるようになった。工場ラインで向き合うための、自分なりのロジックが出来上がった経験でもある。
現在は物流クレーンのメンテナンスをしているが、前職での苦い経験や成功体験が活きていると感じる。物流とは社会を支える大事な業種であり、もしクレーンが故障すると日用品や食べ物が私たちの手元に届かず、日々の生活に影響を与えてしまう。私は、前職の失敗を活かし常に疑いを持ってクレーンを点検、問題箇所を見つけ「ここの部品は大丈夫であろう」などの安易な考えを持たないようにし、チェック項目に入っていない箇所の点検、五感を常に使い問題箇所の早期発見を心がけている。この意識改革は、前職で経験した失敗したからこそ学ぶことができ、私にとって一生の宝物だ。
会社では、さまざまな専門用語が飛び交い、設備によって都度専門知識を学ぶ必要がある。が、改善や修理できた時の達成感もひとしおだ。なにより、少しずつ増えていく経験や知識が私にとって大きなモチベーションになっている。
苦労することや嫌なこと、失敗もある。が、経験は宝であり、諦めず取り組むことが最も重要に感じる今日この頃だ。
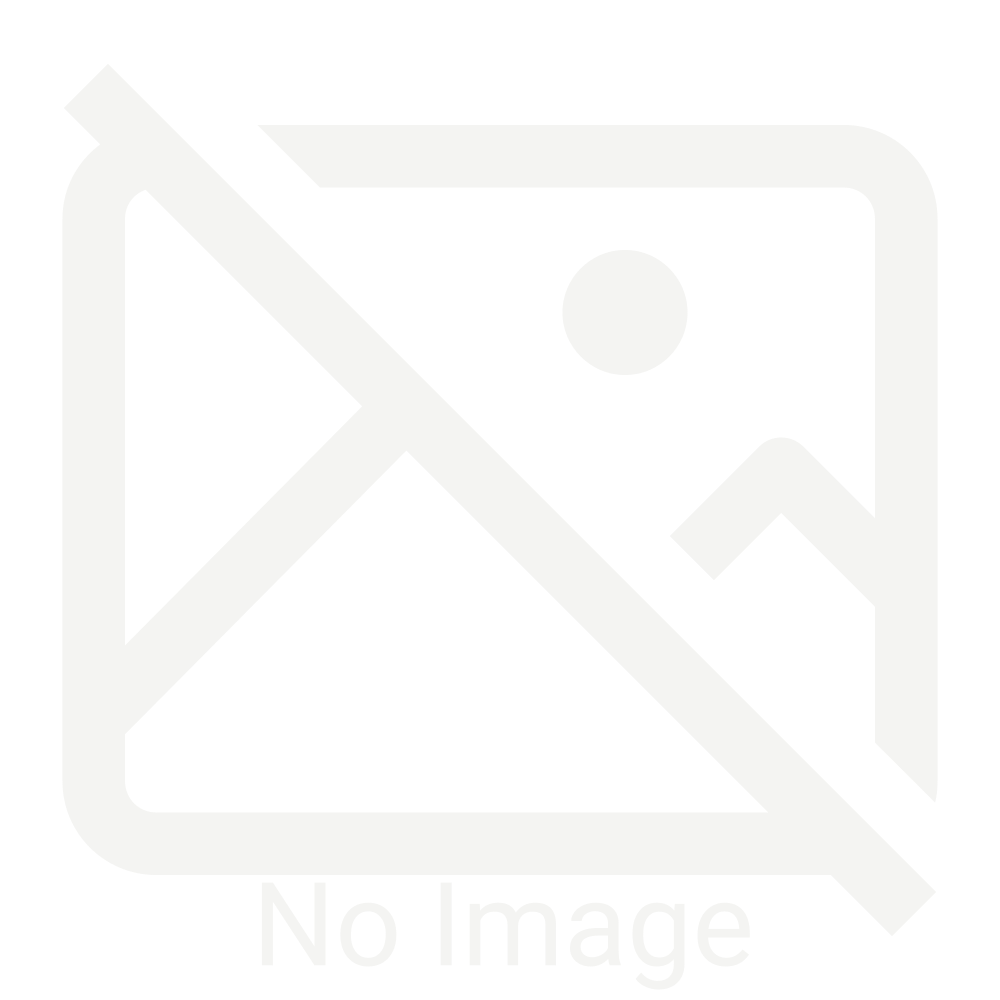
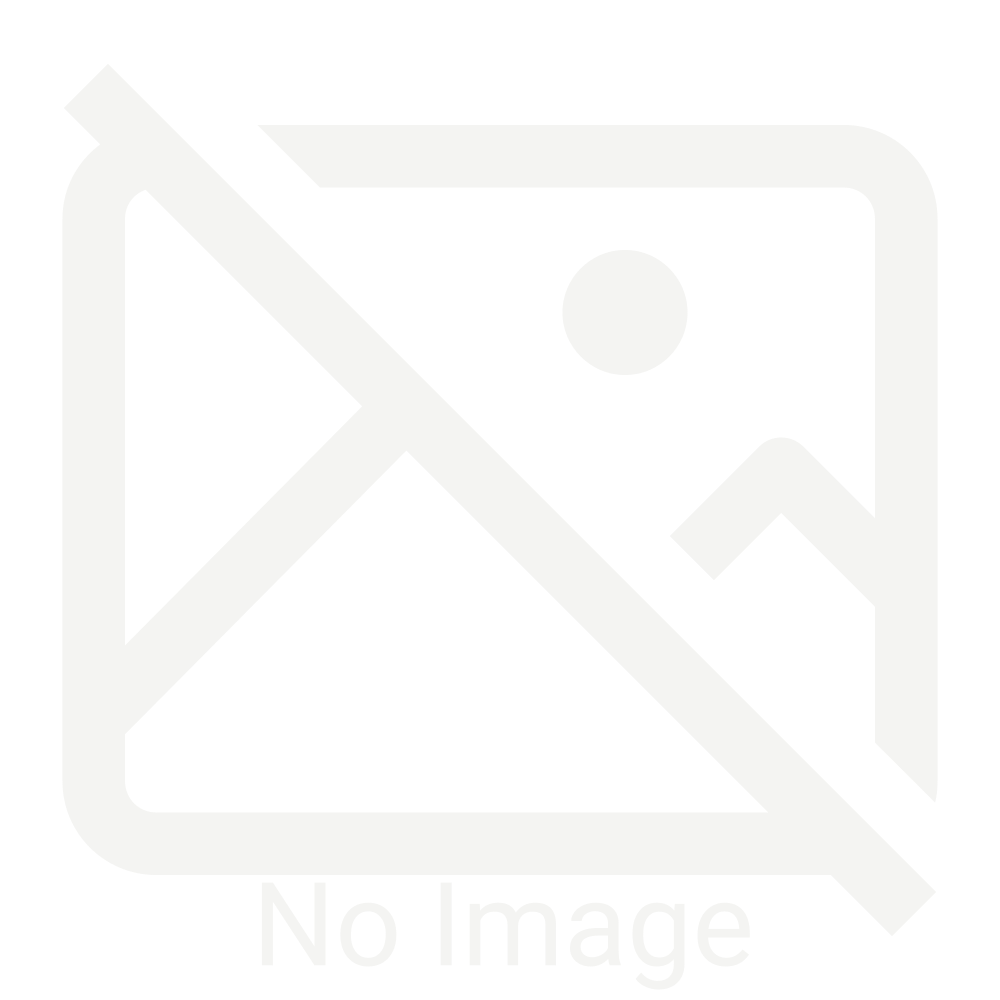
筆者紹介
チャレンジしてみたいと思うことがあれば、
まずはやってみる事を意識しています。
なぜなら、人生は限られているので20年後、50年後に「あの時…挑戦すればよかった…」
と後悔したくないので、まずは迷う前に行動するようにしています。
また、「後悔したくない」というところでは、人との繋がりも同様です。
仕事やプライベートで会った人は、積極的に声をかけてコミュニケーションをとり、一期一会を大切にしています。